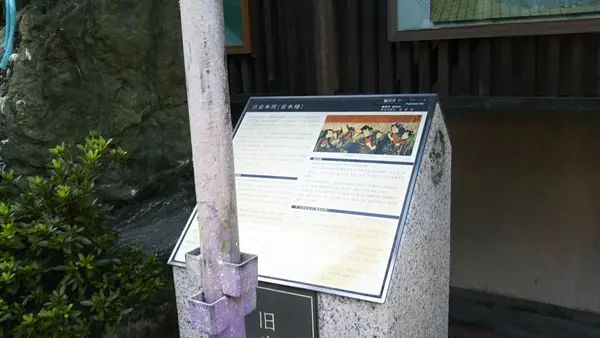まだまだ夏は終わらへん!俺たちの青春が詰まった湘南
神奈川まだまだ夏は終わらへん!俺たちの青春が詰まった湘南
まいどまいど! 関東地方を代表する人気観光地の一つっちゅうたら、やっぱり湘南かもしれまへんな。 場所は神奈川県藤沢市にあり、湘南モノレールや江ノ島電鉄 小田急電鉄が走り抜ける。 向かう先はもちろん江ノ島。 島の中心部には江島神社が鎮座しており、連日、ぎょうさんの観光客・参拝客でにぎわってまんねん。 境内には日本初の野外エスカレーターがあるとか。 ほんでまた名産といえば、海産物であり、特にシラス。 参詣道のいたるところでシラスを販売するレストランがあり、シラスの他、マグロやサザエなど、四季折々の名物を味わうことができまんねん。 さて島を一周したあとには湘南海岸公園へ。 海辺ではヨットやサーフボードを楽しむ人の姿、砂浜や波打ち際で遊んでいる人の姿も。 また、新江ノ島水族館もあり、小さなお子様から楽しめるスポットが盛りだくさん。 そして何よりも小田急電鉄の駅舎が・・・中華料理店!? さあ、俺たちの青春を探しに湘南へ出かけよう。 外は大雪でも俺たちの夏はまだまだこれからやで~♪
-
湘南を代表する景勝地の一つで、神奈川県指定史跡・名勝、日本百景の地。 周囲4km、標高60m。 地質は三浦丘陵や多摩丘陵と同様、第三紀層の凝灰砂岩の上に関東ローム層が乗る。 古来は引き潮の時、洲鼻という砂嘴が現れ、対岸の湘南海岸と地続きとなって歩いて渡ることができたとか。 1923年、関東大震災による隆起で海面上に海蝕台が出現し、隆起海蝕台(岩棚)となった。 海蝕崖の下部には断層線などの弱線に沿って波浪による侵食が進み、海蝕洞が見られる岩屋がある。 江の島の中央部には南北から侵食が進んで島を分断するような地形があり、「山二つ」とも。 東部を東山、西部を西山と呼ぶ。
-

緑の江ノ島
「緑の江の島」と歌われるように照葉樹林と呼ばれる常緑広葉樹林に覆われている。 平安時代、空海、円仁が、鎌倉時代には良信(慈悲上人)、一遍が、江戸時代には木喰が参篭して修行。 1182年、源頼朝の祈願により文覚が弁才天を勧請。 以後、弁才天は水の神・歌舞音曲の守護神とされ、歌舞伎役者や音楽家なども数多く参拝。
-

日本最初の臨海実験所
1858年の日米修好通商条約から1899年の日英通商航海条約発効まで、横浜の外国人居留地に住む人々は、行動範囲を居留地から10里以内に制限された。 その制限範囲内に位置した江の島には、多くの外国人が訪れた。 1877年、東京大学の初代動物学教授エドワード・S・モースはシャミセンガイ研究のため江の島に日本最初の臨海実験所を開いた。
-

日本近代動物学発祥の地・日本最初の野外エスカレーター
アイルランド人貿易商サムエル・コッキングは、与願寺の菜園を買い取り、別荘と庭園の造営。 1885年、熱帯植物を収集栽培し、本格的なボイラーを持つ大型温室やオオオニバスの栽培池を持つという画期的な熱帯植物園が完成するなど、「日本近代動物学発祥の地」の一つとなった。 1959年、江ノ島鎌倉観光は日本初の野外エスカレータ「江ノ島エスカー」を建設。
-
-
滋賀県の宝厳寺・竹生島神社、広島県の大願寺・厳島神社と並ぶ日本三大弁天の一つ。 祭神は宗像三女神。 福岡県宗像市の宗像大社を総本宮とする三柱の女神の総称で、アマテラスとスサノオの誓約で生まれた女神らで宗像大神、道主貴とも。 西方・奥津宮に多紀理比賣命、中央・中津宮に市寸島比賣命、北方・辺津宮に田寸津比賣命を祀り江島大神と総称。 江戸時代まで弁財天を祀り、江島弁天・江島明神とも。 辺津宮境内の奉安殿には八臂弁財天と妙音弁財天が安置。 500年代、欽明天皇の勅命により、江の島の南の洞窟に宮を建立したことに始まる。 神仏習合により金亀山与願寺となった。
-

江島寺から江島神社へ
別当は岩本坊・岩屋本宮(奥津宮)、上ノ坊・上之宮(中津宮)、下ノ坊・下之宮(辺津宮)。 岩本坊は総別当とされ、江島寺とも。 1649年、京都・仁和寺の末寺となり岩本坊のみ岩本院と称する。 1640年、岩本院は幕府からの朱印状を得て上ノ坊、下ノ坊も支配し、全島の権益を握る。 1868年、廃仏毀釈により江島神社へ改称。 僧侶は神職となり、岩本院は参詣者の宿泊施設の旅館となり岩本楼へ改称。
-
-
神奈川県藤沢市江の島にある旅館。 岩本楼の前身は金亀山与願寺(江島神社)の別当職を務めた岩本院。 古くは中の坊と称していたが、岩本坊・岩本院と改名。 上の坊・下の坊と共に与願寺の別当を務めていたが、上の坊・下の坊を支配下に置き、総別当となる。 江戸時代、江の島は観光地として栄え、岩本院も宿坊として人気を集めた。 1862年、初演の歌舞伎、青砥稿花紅彩画(白浪五人男)に登場する弁天小僧は岩本院の稚児をモデルにしたとか。 弁天洞窟風呂は 江の島の岩屋を模した風呂で岩本院時代は稚児を折檻する土嚢であった。
-
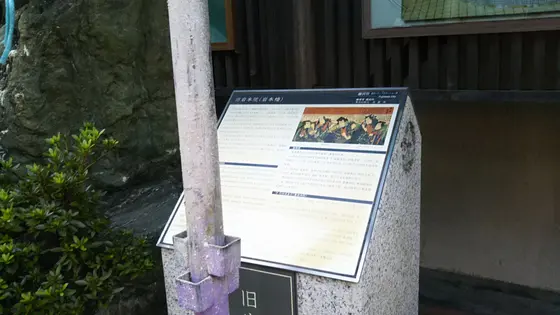
国の登録有形文化財
1873年、神仏分離令により与願寺は廃され江島神社となり、岩本院も岩本楼と改名し旅館となった。 岩本楼ローマ風呂は1930年に完成した洋風の風呂で国の登録有形文化財に登録。
-
-
湘南や太平洋、富士山などを一望することができるインフィニティープールなど温水スパ。
-
1747年、日本三大弁財天の一つに数えられている江島神社の鳥居として創建。 1821年、再建。 現在も江の島弁財天信仰の象徴として信仰を集めている。 江の島道においては現存する三の鳥居で、かつての一の鳥居は遊行寺前に、二の鳥居は洲鼻通りに存在した。
-
その日に捕れたシラスを使ったシラス料理を中心に味わうことができる。 メニューは生しらす料理の生しらす3種丼をはじめ、しらす3種盛り、生しらす寿司、生しらす丼、とびっちょ丼など。 そのほか、マグロやとろサーモン、アジ、赤エビなどの刺身や丼など。
-

江ノ島丼
写真は江ノ島丼。 しらすの他、貝類や魚介類を卵とじ。
-
- アプリで地図を見る
-
神奈川県藤沢市江の島の湘南港防波護岸外端に立つ灯台。 1964年、東京オリンピックのヨット競技場として整備され、灯台も設置。 ヨットハーバーは江の島の北東側海岸にあった岩場を埋め立て完成。 2020年開催予定の東京オリンピックではセーリングの競技会場として決定。
-
神奈川県道305号江の島線は、神奈川県の藤沢市にある県道の一部。 1891年、完成するも台風などにより流される。 道路橋と人道橋で、道路橋は1964年に開催された東京オリンピックのヨット競技のために江の島港が建設されたことに伴って架けられた。 橋長324mの自動車専用橋。 道橋は橋長389mで、以前は有料制であったが自動車専用橋の完成に伴い、渡橋料は無料となった。 江の島に最初に桟橋が架けられたのは明治24年とのことだが、台風時にはよく流されていた。
-
かつて鎌倉には、5つの頭を持つ龍がいて悪行を重ねていた。 天女が舞い降り、天女に恋心を抱く五頭龍を諭し、悪行をやめさせた。 五頭龍は海を離れ、山に姿を変え、現在の藤沢市龍口山となった。 鎌倉市の龍口明神社では五頭龍を祀る。 天女の天下りとともに出現した島が現在の江の島で、天女は江島神社に奉られている弁財天。 江島神社には弁財天堂(奉安殿)があり、裸弁財天像(妙音弁財天)が奉られている。
-
湘南とは神奈川県の相模湾沿岸地方に属する。 由来はかつて中国に存在した長沙国にあった洞庭湖とそこに流入する瀟水と湘江の合流するあたりを瀟湘と呼び、その南部に似ていたことから瀟湘と(洞庭)湖南より一字ずつを取った長沙国湘南県から。 中世中国の湘南では禅宗が発展し、その聖地であった。 日本でも禅宗を保護した鎌倉幕府の北条得宗家が居し、国内初の禅寺の建長寺や円覚寺を擁した鎌倉周辺の地域が、中国の湘南に因むとも。 また古来、相模国と呼ばれ、その「相」に「さんずい」を加えた「湘」として相模国の南部の意味としたとか。
-

湘南の由来
神奈川シープロジェクトにより湘南の定義は沿岸地区地方を指す名称となり、新湘南・湘東と西湘から。 その他、室町時代に中国から日本に移住した子孫・崇雪が小田原に住み、ういろう商人となり、創設した大磯の鴫立庵に建てた石碑に「著盡湘南清絶地」と刻んだものが起源とも。 明治時代、西欧で流行していた海水浴保養が日本でも人気となり、逗子や葉山、鎌倉、藤沢など相模湾沿岸が注目されて別荘地となって発展。
-
-
江ノ島電鉄の江ノ島電鉄線の停車駅の一つ。 1902年、片瀬駅として開業。 1929年、江ノ島駅に改称。
-

江ノ島電鉄
江ノ島電鉄。
-
- アプリで地図を見る
-
モノレール江の島線の停車駅の一つ。 1966年、懸垂式モノレール鉄道として設立。 新幹線0系の開発に関わった鉄道車両技術者・三木忠直は、江の島線敷設にあたって技師長として技術部門の指揮を執り、開業後もしばらく事業に携わった。 1970年、江の島線が開業。 1971年、江の島線が全線開通。 ドイツのヴッパータール空中鉄道と姉妹懸垂式モノレール協定書を締結。 2018年、地上5階建ての駅ビルとして竣工。
-

湘南モノレール
懸垂式モノレール鉄道。
-

ルーフテラス
5階には展望台「ルーフテラス」があり、藤沢市街地を一望することができる。
-
-
道標は、管を用いて鍼をさす管鍼術の考案者で、江の島弁財天を厚く信仰していたといわれる杉山検校が建立。 江の島に鎮座する江島神社に参詣する人々が道に迷うことのないようにと寄進したもの。 この他、市内には道標12基指定。
-
昔ながらの雰囲気が漂う商店街。 商店街には飲食店や居酒屋、雑貨店などが立ち並ぶ。 最寄りは江ノ島電鉄江ノ島電鉄線の江ノ島駅、小田急電鉄江ノ島線「片瀬江ノ島」駅、湘南モノレール江の島線「湘南江の島」駅。 すばな通りの「すばな」とは、近くを並行して海に向かって流れ込んでいる境川の鼻先という意味。 江戸時代、江ノ島に鎮座する江島神社の参詣道としてにぎわい、古くから旅籠や土産屋が軒を連ねていたとか。 戦後には海水浴やマリンスポーツのメッカとして賑わう。
-
神奈川県藤沢市南部、片瀬・鵠沼両地区の相模湾に面する県立公園。 富士山を中心に、右に丹沢、左に箱根・伊豆半島の山々が連なり、伊豆大島、利島まで一望できる。 主に新江ノ島水族館、なぎさの体験学習館、サーフビレッジがある。 1928年、湘南海岸一帯に「魚附砂防林」のクロマツの植林を開始。 1936年、湘南海岸公園道路、通称・湘南遊歩道路という神奈川県道片瀬大磯線の敷設。 自動車道の両側に歩道「逍遙道」、鵠沼・片瀬間には「乗馬道」も設置。 藤沢町会は1940年に予定されていた東京オリンピックに備えて、鵠沼プールを建設するも日中戦争により東京オリンピックは返上、町営鵠沼プールとなった。
-

江の島水族館
太平洋戦争の時期には鵠沼海岸での海水浴は警察の許可を得た市民に限られた。 1954年、江の島水族館が開館。 江ノ島水族館マリンランド、児童海水プール、江の島海獣動物園を開設、江ノ電駐車センター、東急レストハウス、小田急ビーチハウス、江の島へるすせんたー、小田急シーサイドパレス等が建設。
-

県立湘南海岸公園
1960年、県立湘南海岸公園が完成。 1961年、観光センターが開館、小田急鵠沼プールガーデンが開場するも営業終了、鵠沼海浜公園スケートパークに。 赤十字救急法救急員の資格を取得したライフセーバーが監視・救助活動を始め、1963年に湘南ライフガードクラブが組織化。 後の西浜サーフライフセービングクラブとなり、日本初のライフガード組織に。
-

日本のサーファーの最初
ドライブで訪れた米兵が、バーベキューやサーフィンを楽しむようになる。 1961年、湘南学園生の佐賀亜光と松田章が厚木基地の海軍パイロットで中尉のトム、星条旗新聞の記者で海洋学者のガース・A・ジェーンズ、全米トランポリンチャンピオンのフィル・ドリップスらからロングボードを操るようになり、これが日本サーファーの最初。 1962年、佐賀兄弟らは日本初のサーファークラブ「サーフィングシャークス」を組織。
-

湘南サウンドと東洋のマイアミビーチ
サーファー等で競技会を開催し全国組織日本サーフィン連盟(NSA)に。 1950年代、石原慎太郎の芥川賞小説太陽の季節が映画化されて太陽族を生み、加山雄三の若大将シリーズや加瀬邦彦のザ・ワイルドワンズ、ブレッド&バター、尾崎紀世彦、サザンオールスターズ、テミヤン等「湘南サウンド」は注目を集めた。 1959年、米国フロリダ州マイアミビーチ市との姉妹都市提携、「東洋のマイアミビーチ」として売り出す。
-

日本初
1960年、東急レストハウスで第1回輸入車ショウ(外車ショー)が開催。 1964年、東京オリンピックの会場の一つとなり、日本一の海水浴場との異名も。 1983年、ハワイ生まれのビーチスポーツボディボードは日本における最初。 1987年、鵠沼海岸で日本初のビーチバレー公式大会「ビーチバレー・ジャパン」が開催。 1989年、日本初のスポーツカイト(スタントカイト)競技会が開催。
-

日本初のビーチテニス講習会
1991年、明治大学ラグビー部のローカルルールゲーム、ビーチ・タッチ・フットボールの最初の公式戦が開催、世界初の公式戦に。 1995年、日本初のビーチバレー常設コートが設置。 ビーチアルティメット、ザ・ビーチ選手権大会が開催、日本ビーチスポーツの拠点に。 2007年、ビーチバレー常設コートで日本初のビーチテニス講習会が開催、日本ビーチテニス連盟主催の鵠沼Beach Tennisオープン大会が開催。
-
-
1950年代、六大映画会社の一つ日活社長の堀久作氏は湘南海岸に水族館建設を計画。 1952年、江ノ島水族館を設立し、1954年に「水族館(1号館)」が開業。 魚類を飼育する部分と、標本やクラゲの飼育、エドワード・S・モースの江ノ島臨海実験所 に於ける功績を称える展示が中心。 1957年、児童海水プールの営業開始するも1963年に閉鎖され、3号館「海獣動物園」が開園。 1957年に公開された日活映画「鯨箱根を越ゆ」では上映時間29分、江の島水族館マリンランド開園時の様子の記録映画が公開され、ハナゴンドウが静岡県の伊豆・安良港から輸送される様子が描かれている。
-

江の島海獣動物園
1958年、日本初のテレビアニメーション「もぐらのアバンチュール」とともに「江ノ島水族館」という短編映画がカラーで放送。 1960年代、湘南海岸公園の敷地内に「マリンランド(2号館)」と「海の動物園」が増築。 開園当初は「江の島海獣動物園」と称していた。
-

新江ノ島水族館に改称
1967年、水産庁オットセイ委託飼育場の表示許可を受け、日本における唯一のオットセイ飼育場となる。 1977年、日本におけるミナミゾウアザラシの雄個体の中では最長飼育記録を樹立。 1982年、江の島海の動物園と改称。 2001年、施設老朽化を理由に施設の建て替え、新江ノ島水族館に改称。 鯨類博物館鯨の胎児の液浸標本や龍涎香、マッコウクジラの下あごの骨が展示。
-
- アプリで地図を見る
-
小田急電鉄江ノ島線の停車駅の一つ。 駅舎は竜宮城を模したデザインであることが特徴で、関東の駅百選に選定。 1926年、東海土地電気は江ノ島電気鉄道(江ノ島電鉄と改称)に譲渡。 1928年、江ノ島電気鉄道は東京電燈経営の軌道線(現在の江ノ島電鉄線)を買収。 1929年、鎌倉郡川口村西浜で開業。 2020年、新駅舎が完成。 江ノ島電鉄は「江ノ島駅」であり、片瀬海岸が付近にあることから「片瀬江ノ島」と命名。
-

竜宮造り
旧駅舎のデザインであった神殿調を引き継ぎ、神社仏閣に用いられる「竜宮造り」の技法を取り入れた。 コンコースには新江ノ島水族館のクラゲ水槽を設置。
-