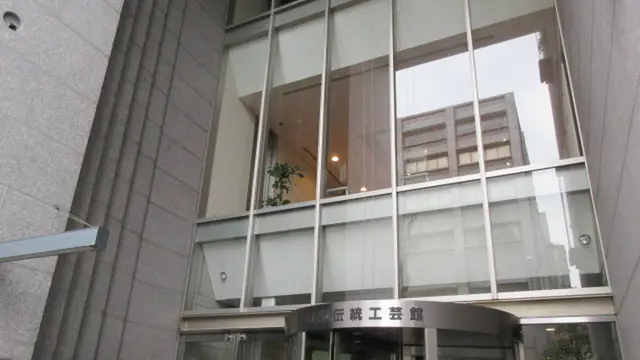
本能寺の変と三井財閥の歴史を学ぶ
京都本能寺の変と三井財閥の歴史を学ぶ
まいどまいど! 今回は京都の中心部に位置する中京区を案内していきまひょ! 中京区には大阪・梅田から走る阪急電車京都線の終点である烏丸や河原町にあたり、周辺は繁華街。 毎年夏になると本格的な祇園祭が開催され、まさに、人、人、人・・・。 また、京阪電車本線の三条、神宮丸太町からも押し寄せ、年中、観光客でにぎわうエリア。 地名・元本能寺南町には、織田信長と明智光秀の戦いの舞台ともなった本能寺跡があり、今でも、歴史の教科書などでは「本能寺の変」として語り継がれている場所。 まあ、せやけど、周辺は閑静な住宅街となっていて、面影は一切おまへんけど、石碑だけが当時を物語ってはりまんな。 その他、三井財閥の原点ともいえる三井両替商跡があり、かつての三井高利はんも付近を歩いてはりましたんやろな。 ほんでその他、六角堂がおまして、ここでは聖徳太子、小野妹子ゆかりの地として有名でんな。 また、六角堂では華道、池坊発祥の地としても知られておます。 その他、京都の伝統を守る工芸館など、歴史的にも文化的にも、おもろいエリア。 中京区の郊外もおもろおまっせ。
-
京都伝統香華大学校に属し、世界に誇る京都の伝統工芸の魅力を発信することを目的に開設された博物館。 フランスやイタリアなど海外との交流展示を行っている
-
京町屋と着物の長襦袢のミュージアムとして知られ、祇園祭期間中の「屏風祭」の様子が再現されている他、明治時代から大正時代にかけての長襦袢や染色資料を展示・保存している。 1926年、建設。 和室部分は上坂浅次郎、洋館部分は武田五一が設計。 江戸時代、荻野元凱が医院を開業。 大正時代、豪商・四代目井上利助氏が元凱時代をそのままに新築し、川崎家が使用していた。 主屋座敷の東山三十六峰をモチーフにした竹内栖鳳の欄間などは近代京町家の貴重な歴史資料となっており、京都の伝統的な「大塀造」建築の代表例ともいわれている。
-

付近にはかつて後鳥羽上皇の御所が置かれていた。 江戸時代、龍野藩脇坂家の京藩邸となった。 1686年、越後屋呉服店の創業者である三井高利が両替店を開いた。 三井高利は江戸、大坂、京の三都にまたがる両替事業の本部とし、貸付、為替、金銀通貨の交換などを行う総合金融業として事業を統括した。 1691年、幕府から金銀御為替御用を命ぜられ、地位を確立させた。 明治時代、日本で初めてとなる私立銀行の三井銀行を設立した。
-
1415年、日隆により、寺号「本応寺」として創建。 日隆は妙本寺4世・日霽に師事、法華経の解釈を巡って本迹勝劣を主張した日隆は、妙本寺5世・月明と対立。 本応寺は月明によって破却、日隆は河内三井の本厳寺、尼崎の本興寺へ移った。 帰洛して大檀那・小袖屋宗句(山本宗句)の援助により、本応寺を再建。 1433年、檀那・如意王丸から六角大宮の西、四条坊門の北に土地の寄進を受けて再建し、寺号を「本能寺」と改称。 以後、法華経弘通の霊場として栄え、中世後期には洛中法華21ヶ寺の一つとなった。 応仁の乱後、京都復興に尽力した町衆の多くは法華宗門徒で、法華宗の信仰が浸透し「題目の巷」と呼ばれた。
-

本能寺
天文法華の乱にて延暦寺・僧兵により、堂宇は焼失し、一時、堺の顕本寺に避難。 1582年、本能寺に滞在した織田信長を家臣・明智光秀が謀反を起こして襲撃。 信長の嫡男で織田家当主信忠は、妙覚寺から二条御新造に退いて戦ったが、館に火を放って自刃。 中国大返しで畿内に戻った羽柴秀吉に山崎の戦いで敗れ、光秀も没した。 1591年、豊臣秀吉の命で移転。
-
-
公儀呉服師を世襲した京都の豪商。 正式には中島氏。 代々、茶屋四郎次郎を襲名する習わしであった。 1500年代、信濃守護小笠原長時の家臣・中島明延が武士を廃業、京都で呉服商を創業。 茶屋の屋号は、将軍の足利義輝が明延の屋敷に茶を飲みに立ち寄ったことに由来。 初代清延は本能寺の変の際、堺に滞在中の徳川家康一行に早馬で一報し、後世に「神君伊賀越」といわれた脱出劇では、物心ともに支援を行った。 これにより、徳川家の呉服御用を一手に引き受けるようになった。 二代清忠は、淀川過書船支配など物流の取締役に任命。 関ヶ原の戦後、京都の情勢不穏を家康に進言、京都所司代設置のきっかけを作る。
-

茶屋四郎次郎
板倉勝重が所司代に就任し上方五カ所(京都・大坂・奈良・堺・伏見)町人の御礼支配、京都町人頭に任命。 三代清次は家康の側近で、長崎奉行に就任、長崎代官補佐役の役割も務め、朱印船貿易で巨万の富を築いた。 角倉了以の角倉家、後藤四郎兵衛の後藤四郎兵衛家と共に京都町人頭を世襲、「京の三長者」とも。 鎖国後、朱印船貿易特権を失い、呉服師・生糸販売を専業としたが、納入価格を巡って呉服御用差し止めを受けて廃業。
-
-
1549年、大陸からキリスト教文化が伝来する。 以後、全国各地に南蛮風の教会堂のが建てられ、徳川幕府によるキリスト教禁教まで続いた。 1551年、日本における本格的な教会堂が山口の大道寺として建立。 以後、豊後のデウス堂、平戸の天門寺、有馬の正覚寺、長崎、京都、堺、安土、大坂、金沢、駿府、江戸など全国各地に教会が建設され、南蛮寺、南蛮堂等と呼ばれた。 都の南蛮寺は1574年、京に建てていた教会堂の老朽化に伴って再建が決定し、日本に建てられた教会堂でも最大級規模となった。 正式名は、被昇天の聖母教会。 1587年、豊臣秀吉によるバテレン追放令後に破壊された。
- アプリで地図を見る
-
京都で採れた新鮮な野菜「京野菜」を中心に使用したレストラン。 店内ではカウンター席とテーブル席がある。 メニューは、朝食おばんざいセット、おばんざいセット、湯葉丼セット、ちょい呑みセットなど。 セルフサービスとなっていて、メニューを選択後、好みの小鉢を選択できる。 湯葉丼セット、おばんざいセットは6つまで、朝食おばんざいセットは4つまでなど。 小鉢は、毎日日替わりで10種類以上、ごはんは白米と雑穀米、湯葉丼から選択できる。 1978年創業。
-

湯葉丼セット
湯葉丼セット、小鉢は6つと汁物。
-
-
戦国時代、堺の豪商(武具商あるいは皮革商)、茶人として活躍。 幼名、松菊丸。 通称、新五郎。 名乗、仲材。 1502年、大和国吉野郡(奈良県)生まれ。 三好氏の庇護を受け、和泉国の堺(大阪府堺市堺区)に定住。 1525年、京都に居を構え、連歌師をしていた。 1528年、文化人の三条西実隆に師事し、古典や和歌について学ぶ。 朝廷に献金を行い、因幡守に任ぜられる。 加賀の一向一揆内部で内紛「享禄の錯乱」が勃発し、山科本願寺のため、山科へ向かう。 禅宗である臨済宗大徳寺の古嶽宗亘のもとで出家、紹鷗の法名を受ける。 堺に戻り、連歌会の発句を実隆に依頼。 大徳寺の末寺である南宗寺に参禅。
-

大黒菴武野紹鴎邸址の碑
大林宗套より嗣法し、一閑斎と号し、大黒庵主となる。 奈良の塗師で茶人の松屋久政他三人を茶会に招待し、玉澗の水墨画「波図」を床に飾り、唐物名物の松島の茶壺を用いた。
-
-
1868年、土蔵が建設。 1897年、会所家が建設。 その他、地蔵堂から構成。
































